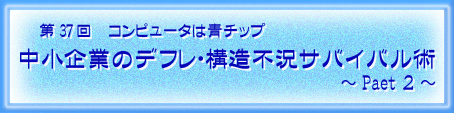
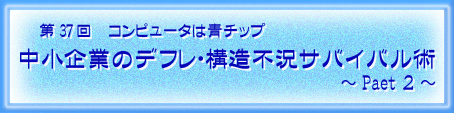
| 9.11のWTC崩壊の中継は衝撃的だった。しばし呆然となった。しばらくニュースのはしごをし、にわか政治評論家、軍事評論家になり国家の正義とはいかにあるべきか、今後の世界はどうなっていくのか、とか考えてみたが、ふと我に返ると、これは景気はもっと悪くなるぞ、我社はどうなるのか、どうすれば良いのかという一種の恐怖心が襲ってきた。 半年前構造改革の断行を標榜して誕生した小泉内閣だが、この間の成果はNothingであるばかりか、改革の具体的中身、筋道すら明らかになっていない。またぞろ従来型の景気対策や党利党略の選挙制度いじりなど、その場しのぎの改革が実行されるのみだろう。どうやらこの国は破綻の道の入り口に差し掛かってもう後戻りできない一歩を踏み出したような気がしてならない。 以前より私は一中小企業人が天下国家のことを論じても仕方ない、そこは政治家や政治、経済の専門家にお任せして、第三の波ともいわれる大変革に我社はどう対応したら良いのかということを皆様とともに考えてきた。しかし本当にこういう態度でよいのか疑問を持ち、少なくとも10年以上に渡る不況の原因、この10年行われてきた様々な対策の成否、今後の日本経済の見直し、日本経済再生の為のとるべき対策について自分なりに考えてみた。 結論からいうと不況の原因は、中国の市場経済への登場やASEAN諸国が力をつけたことと、IT技術を核としたイノベーションに企業が乗り遅れた結果日本型経営モデルの収益力が低下したこと、また個々の企業がバブル崩壊による資産価格下落に伴い負債圧縮に走ったことである。過去10年で150兆円に上る景気対策が行われたが、効果はあがっていない。返済不可能の財政赤字を負ったという意見と、大恐慌を回避できたと評価する意見とがあるが、本格的な回復策でないことは一致していて、金融機関の不良債権処理、財政再建もバブル崩壊の対症療法に過ぎない。では日本経済再生のとるべき手段は何か。「日本経済の活性化は、企業収益の回復によってしか実現しない。具体的には、東アジアの工業化とITの登場という新しい条件下で収益をあげうる、新しいビジネスモデルを構築することだ。それに従って事業内容を転換し、企業を再生させる必要がある」「民間企業の改革は、第一義的には民間企業の課題だ。経営者が状況変化を正しく認識し、リーダーシップを発揮する必要がある」「『政府の積極的なイニシアチブで事態が好転する』という幻想から目を覚ます必要がある」(以上2001.10.22日経新聞「政府依存脱し真の改革」野口悠紀雄氏より引用) 民間企業が以上の過程を経て、日本経済が再生するには最低5〜10年はかかると思われる。 国が行う短期的な政策は、一時しのぎにはなっても我社の存続にはまったく+にならないと考えるべきで、現在の苦境を景気のせいにしてはならない。なぜならこの10年続いた不況が今後も5年、10年は続くので、景気回復をあてにはできないからだ。企業の存続の条件はどのような条件下においても「イノベーション」である。結局自社で出来ることは前回と同じ内容になってしまった。要するに自助努力あるのみである。 <佐藤 文弘> |
| /参考文献 吉田和男「日本経済再建『国民の痛み』どうなる」 講談社 リチャード・クー「日本経済 生か死かの選択」 徳間書店 山家悠紀夫「『構造改革』という幻想」 岩波書店 |
| 01年11月号TOPへ |